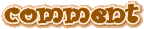プロフィール
HN:
三浦 真司
Webサイト:
性別:
男性
職業:
楽習堂塾長
自己紹介:
岐阜県羽島郡笠松町の学習塾の経営者です。
【出身高校】
岐阜県立岐阜高等学校
【出身大学】
慶應義塾大学経済学部
【出身高校】
岐阜県立岐阜高等学校
【出身大学】
慶應義塾大学経済学部
最新記事
(02/01)
(12/12)
(12/04)
(11/03)
(08/22)
P R
2019.06.01
エース家紋ビスケットの謎(7)
エース家紋ビスケットで最上家の家紋として紹介されたのは「丸に二つ引き」という家紋です。「エース家紋ビスケットの謎(1)」で示した二番目の写真の中の、家紋一覧の右下にある、丸に二つ線の入ったものが「丸に二つ引き」。
しかし、家紋に詳しい人がこの家紋から普通イメージする家は、最上ではないと思います。「丸に二つ引き」から通常真っ先に思い浮かぶのは、室町時代に将軍家になった足利家なんです。
それではなぜ、足利家の家紋が最上家の家紋にもなったのか?足利家の一族に斯波家というのがあります。室町時代になると管領(将軍の筆頭補佐官)にしばしばなった家です。この斯波家の一族が、室町時代に東北にやって来て、陸奥国を統括する奥州探題という役職につき、大崎家と名乗るようになりました。その一族が最上家なんですね。つまり、最上家は足利家の一族の一族の一族なので、足利一族なんです。ということで、足利家の家紋が最上家の家紋にもなったわけですね。
足利一門だったら、たいてい「丸に二つ引き」なんです。この家紋を持った戦国大名として、最上義光以外に有名なのは、今川義元ですね。今川家は、足利家の一族である吉良家(『忠臣蔵』の吉良上野介の家)の一族なので、やっぱり足利一族なんですね。足利一族は室町時代に全国に広がったので、「丸に二つ引き」は室町時代の後期から始まった戦国の世にはよく登場するんです。
以上で、この話題はおしまい。
しかし、家紋に詳しい人がこの家紋から普通イメージする家は、最上ではないと思います。「丸に二つ引き」から通常真っ先に思い浮かぶのは、室町時代に将軍家になった足利家なんです。
それではなぜ、足利家の家紋が最上家の家紋にもなったのか?足利家の一族に斯波家というのがあります。室町時代になると管領(将軍の筆頭補佐官)にしばしばなった家です。この斯波家の一族が、室町時代に東北にやって来て、陸奥国を統括する奥州探題という役職につき、大崎家と名乗るようになりました。その一族が最上家なんですね。つまり、最上家は足利家の一族の一族の一族なので、足利一族なんです。ということで、足利家の家紋が最上家の家紋にもなったわけですね。
足利一門だったら、たいてい「丸に二つ引き」なんです。この家紋を持った戦国大名として、最上義光以外に有名なのは、今川義元ですね。今川家は、足利家の一族である吉良家(『忠臣蔵』の吉良上野介の家)の一族なので、やっぱり足利一族なんですね。足利一族は室町時代に全国に広がったので、「丸に二つ引き」は室町時代の後期から始まった戦国の世にはよく登場するんです。
以上で、この話題はおしまい。
PR

 管理画面
管理画面