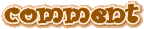プロフィール
HN:
三浦 真司
Webサイト:
性別:
男性
職業:
楽習堂塾長
自己紹介:
岐阜県羽島郡笠松町の学習塾の経営者です。
【出身高校】
岐阜県立岐阜高等学校
【出身大学】
慶應義塾大学経済学部
【出身高校】
岐阜県立岐阜高等学校
【出身大学】
慶應義塾大学経済学部
最新記事
(02/01)
(12/12)
(12/04)
(11/03)
(08/22)
P R
2019.05.27
エース家紋ビスケットの謎(4)
伊達家の家紋使用の可否はどう決められているのか?
…という話をする前に、政宗以降の伊達家がどうなったかということについての、少し話をしようかと。
政宗によって基礎が築かれた仙台伊達藩。途中に危機が訪れることもありました。危機の最たるものは、17世紀後半に生じた、いわゆる伊達騒動でしょうね。人形浄瑠璃や歌舞伎の有名演目『伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)』のモデルになった事件で、昔の大河ドラマ(平幹二郎主演の『樅ノ木は残った』もこの事件を題材にした話。
とはいえ、まぁ何とか危機を潜り抜けて、仙台伊達藩は幕末まで存続できたのでした。幕末動乱期はそんなに目立った活動をしなかったのですが、最後になって仙台藩は政局を大きく左右する働きをすることになったのです。江戸城の無血開城の後、東北諸藩は薩長主体の新政府に対抗して奥羽越列藩同盟を結成、仙台藩はその盟主的地位に立ち、戊辰戦争を長期化させる原因を作ったのです。
かくして、幕末動乱の渦中に身を投じるに至った仙台伊達藩。やはり独眼竜軍団の血を引く強者ども、その勇猛果敢な戦ぶりに、流石の薩摩や長州も恐れおののかずにはいられなかったのだった!(>_<)
…というわけでは、ありませんですた。(/・ω・)/
戊辰戦争期の仙台軍は、すぐ逃げることで有名になってしまったのです。「大砲がドンと鳴ったら五里(約20キロメートル)逃げる」というので、ついた仇名が「ドンゴリ」…(*_*;。幕末の諸藩軍の中で、仙台軍ほど評判の悪いところって、他にあるんだろうか…?
結局、列藩同盟結成してから四か月程経って、仙台藩は新政府軍に降伏。62万石から28万石に厳封されて、廃藩置県を迎えたのでした。
続きは次回に。
…という話をする前に、政宗以降の伊達家がどうなったかということについての、少し話をしようかと。
政宗によって基礎が築かれた仙台伊達藩。途中に危機が訪れることもありました。危機の最たるものは、17世紀後半に生じた、いわゆる伊達騒動でしょうね。人形浄瑠璃や歌舞伎の有名演目『伽羅先代萩(めいぼくせんだいはぎ)』のモデルになった事件で、昔の大河ドラマ(平幹二郎主演の『樅ノ木は残った』もこの事件を題材にした話。
とはいえ、まぁ何とか危機を潜り抜けて、仙台伊達藩は幕末まで存続できたのでした。幕末動乱期はそんなに目立った活動をしなかったのですが、最後になって仙台藩は政局を大きく左右する働きをすることになったのです。江戸城の無血開城の後、東北諸藩は薩長主体の新政府に対抗して奥羽越列藩同盟を結成、仙台藩はその盟主的地位に立ち、戊辰戦争を長期化させる原因を作ったのです。
かくして、幕末動乱の渦中に身を投じるに至った仙台伊達藩。やはり独眼竜軍団の血を引く強者ども、その勇猛果敢な戦ぶりに、流石の薩摩や長州も恐れおののかずにはいられなかったのだった!(>_<)
…というわけでは、ありませんですた。(/・ω・)/
戊辰戦争期の仙台軍は、すぐ逃げることで有名になってしまったのです。「大砲がドンと鳴ったら五里(約20キロメートル)逃げる」というので、ついた仇名が「ドンゴリ」…(*_*;。幕末の諸藩軍の中で、仙台軍ほど評判の悪いところって、他にあるんだろうか…?
結局、列藩同盟結成してから四か月程経って、仙台藩は新政府軍に降伏。62万石から28万石に厳封されて、廃藩置県を迎えたのでした。
続きは次回に。
PR

 管理画面
管理画面